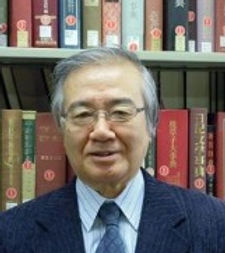六朝学術学会 歴代会長・沿革
沿革
1997 (平成9)年
4月13日 六朝学術学会 設立総会(斯文会館講堂)
7月25日 ~8月2日 第1回 日中陶淵明学術討論集会/陶淵明関係遺跡実地踏査
8月13日 役員選出/『六朝学術学会報』原稿募集
1999(平成11)年
4月1日 第1回 研究例会(青山学院大学)
7月17日 第2回 研究例会(青山学院大学)
11月31日 第3回 六朝学術学会大会(斯文会館講堂)
12月 『六朝学術学会報』第一輯 刊行
2000(平成12)年
4月1日 第3回 研究例会(青山学院大学)
7月29、30日 魏晋南北朝文学与文化国際学術研討大会
8月12~20日 第2回 日中陶淵明学術討論集会/「『桃花源記』ゆかりの地を訪ねる」ツアー
10月29日 第4回 六朝学術学会大会(斯文会館講堂)
2001(平成13)年
3月 役員改選/『六朝学術学会報』第二輯 刊行
4月 第4回 研究例会(青山学院大学)
7月 第5回 研究例会(青山学院大学)
11月11日 第5回 六朝学術学会大会(斯文会館講堂)
2002(平成14)年
1月 第6回 研究例会(青山学院大学)
3月 『六朝学術学会報』第三輯 刊行
7月13日 第7回 研究例会
同日 シンポジウム
「六朝詩人論作家論は同のように可能か―興膳宏著『乱世を生きる詩人たち―六朝詩人論』を読んで―」
11月10日 第6回 六朝学術学会大会(斯文会館講堂)
2003(平成15)年
3月15日 第8回 研究例会
7月5日 第9回 研究例会
11月2日 第7回 六朝学術学会大会(斯文会館講堂)
2004(平成16)年
3月21日 運営委員会
3月31日 第10回 研究例会(於 青山学院大学)
(1)「南北朝間の使節往来における文化的側面について」 堀内 淳一 氏(東京大学大学院)
(2)「舟の文学」 渡邉 登紀 氏(京都大学大学院)
(3)「六朝修辞主義文学の遊戯性をめぐって」 福井 佳夫 氏(中京大学)
同日 『六朝学術学会報』第五輯 刊行
7月17日第11回 研究例会(於 青山学院大学)
(1)「後漢の辺境統治と三国の分立」 石井 仁 氏(駒澤大学)
(2)「東晋・劉宋初期の文学に対する一考察~呉歌と西曲の関係を起点として」 佐藤 大志 氏(広島大学)
(3)「文選集注の書写者について」 神鷹 徳治 氏(明治大学)
9月3日 運営委員会
11月14日
第8回 六朝学術学会 大会・総会・理事評議委員会(於 斯文会館講堂)
研究発表
(1)「『漢晋春秋』に見る三国正統観の展開」 田中 靖彦 氏(東京大学大学院)
(2)「『世説新語』の編纂意図について」 土屋 聡 氏 (九州大学大学院)
(3)「『三都賦』制作の意図とその受容について」 戸髙 留美子 氏(お茶の水女子大学院)
(4)「香りを含む女性たち―漢魏晋期における女性と芳香の表現について」 狩野 雄 氏(相模女子大学)
(5)「詠物の文―六朝の謝啓について」 道坂 昭廣 氏(京都大学)
記念講演
「許嵩と『建康実録』」 安田 二郎 氏(東北大学 名誉教授)
総会
2005(平成17)年
3月25日 第12回 研究例会(於 青山学院大学)
(1)「南朝における文学と政治―劉宋孝武帝期を中心に」 山崎 益裕 氏(中央大学大学院)
(2)「祠廟空間と文芸序説」 佐野 誠子 氏(京都大学人文科学研究所)
(3)「鮑照詩のは奇想性―特にその言語の面からの検討を通して」 向嶋 成美 氏(筑波大学)
3月31日 『六朝学術学会報』第六輯 刊行
2006~2010年
工事中

2011(平成23)年
○例会
5月21日(土) 第23回研究例会 於 二松学舎大学
[報告]
・正月十五日の行事について 青山学院大学大学院 冨田 絵美
・「魏都賦」旧注に見える特徴について―「三都賦」劉逵注との比較を通して
九州大学大学院 栗山 雅央
・遠望と遐想──六朝文学の主題として 東京大学 齋藤 希史
○大会
11月5日(土) 第15回大会 於 二松学舎大学
[報告]
・阮籍「詠懐詩」に描かれる命 お茶の水女子大学大学院 鄭 月超
・陶淵明「讀山海経」詩の連作的構造-超越と回帰- 筑波大学大学院 加藤 文彬
・陶淵明「孟府君伝」に関する考察―「君」に着目して― 明治薬科大学非常勤講師 大立 智砂子
・六朝の総集における先秦両漢の「作品」について 奈良女子大学 谷口 洋
[記念講演]
・西涼楽の形成と展開 京都府立大学 渡辺 信一郎
○刊行物 『六朝学術学会報』第12集(3月末日)
2012(平成24)年
◎例会
3月17日(土)第24回研究例会 於奈良女子大学
[報告]
・ 六朝の人物評論と文藝批評 京都大学大学院 成田健太郎
・ 陶謝詩における身体表現 愛知教育大学 堂薗 淑子
・ 徐陵と庾信の駢文について 京都大学 道坂 昭廣
12月8日(土)第25回研究例会 於二松学舎大学
[報告]
・ 阮籍「詠懐詩」にみえる感情表現の特質 お茶の水女子大学大学院 鄭月超
・ 六朝期の納涼を描く詩について 早稲田大学非常勤講師 高芝麻子
・ 劉孝標をめぐる人々―南朝政治史における三斉豪族― 東海大学非常勤講師 榎本あゆち
◎大会
6月16日(土) 第16回大会 於二松学舎大学
[報告]
・ 魏文帝の詩歌にみえる感情表現の特質―「腸」を中心に― 二松学舎大学大学院 亀井 有安
・ 皇甫謐の著作がえがき出す出処―『高士伝』『帝王世紀』の意義― 奈良女子大学大学院 横山きのみ
・ 新王朝への態度―北斉滅亡時の士人たち― 京都大学非常勤講師 池田 恭哉
[特別講演]
・ 中国大陆六朝文学研究的趋向及我的一点看法 復旦大学 戴燕
[記念講演]
・ 江南文化の系譜―建康と洛陽 中央大学 妹尾達彦
◎刊行物 『六朝学術学会報』第13集(3月末日)
2013(平成25)年
◎例会
3月16日(土) 第26回研究例会 於 県立広島大学
[報告]
・ 白道猷をめぐる聖賢伝承―天台山を初めて開いた人物
について― 京都大学非常勤講師 佐藤 礼子
・ 晋宋の志怪と地方の伝承 奈良女子大学 大平 幸代
・ 都市の荒廃を描く文学―鮑照「蕪城賦」をめぐって― 広島大学 佐藤大志
12月7日(土) 第27回研究例会 於 愛知大学
[報告]
・ 北宋の唐庚から盛唐の杜甫そして南朝梁の何遜へ
― 一句法から見た受容のありかた―
愛知大学 矢田 博士
・ 赤壁は何を以て実在するか 愛知大学 木島史雄
・ 京都国立博物館所蔵敦煌道経小考 名古屋大学 神塚淑子
◎大会
7月6日(土) 第17回大会 於 二松学舎大学
[報告]
・ 西晋の宗室統制の変遷と八王の乱の原因 青山学院大学院 島田悠
・ 「桓山之悲」小考―「親子の別れ」か「兄弟の別れ」か― 香川大学 池田恭哉
・ 『文選』序文と詩の六義―詩の伝統の継承と離反― 二松学舍大学 牧角悦子
・ 「明胆論」に見る嵆康の思惟の原型 青山学院大学名誉教授 大上正美
[ 記念講演]
・ 杜甫と前代の詩人たち 京都大学名誉教授 興膳宏
◎刊行物『六朝学術学会報』第14集(3月末日)
2014(平成26)年
◎例会
○3月15日(土)第28回研究例会 於 二松学舎大学
[報告]
・ 南朝梁・蕭綱「文章放蕩論」試論 高崎経済大学 大村和人
・ 中国における畜類償債譚の受容 聖学院大学非常勤講師 福田素子
・『 抱朴子』の文学論と「道」への指向 早稲田大学 渡邉義浩
○12月6日(土)第29回研究例会 於 二松学舎大学
[報告]
・「 箕踞」と「竹林七賢」 中央大学院 河野 哲宏
・ 阮籍「詠懐詩」における価値観をめぐって 二松学舍大学院 小島朋子
・『 捜神記』における天人相関説と五気変化論 早稲田大学 渡邉義浩
◎大会
○6月21日(土) 第18回大会 於 二松学舎大学
[報告]
・ 『後漢書』南蛮伝と劉宋における「南蛮」の政治的意義 大東文化大学院 三津間弘彦
・ 顔延之「北使洛」に見える「懐古詩」の形成 早稲田大学非常勤講師 住谷孝之
・ 『捜神後記』における仏教関連話―陶淵明と仏教の関係 再考を兼ねて 和光大学 佐野誠子
・ 『 文選』編纂に見る「文」意識 二松学舎大学 牧角悦子
[記念講演]
・ 六朝義疏学から唐『五経正義』へ 二松学舎大学教授 野間文史
◎刊行物
『六朝学術学会報』第15集(3月末日)
2015(平成27)年
○例会
第30回研究例会 3月14日(土) 於東北大学
・ 六朝人の論法─否定辞に着目して 塚本信也
・ 台湾布袋戯における三国志脚本について 福山泰男
・ 南朝公主の婚姻 川合安
第31回研究例会 12月19日(土) 於福岡大学
・ 干宝『捜神記』における山川記事について 雁木誠
・ 潘岳「笙賦」をめぐって 上原尉暢
・ 李白の「静夜思」は秋の詩か? 松浦崇
○大会
第19回大会 6月20日(土) 於二松学舎大学
・ 六朝期の賦の評価より見る『文選』賦類の編纂について 栗山雅央
・ 甄琛から見る北魏という時代 池田恭哉
・ 劉宋の七夕詩について 渡邉登紀
・ 庾信以前、庾信以後―庾信の碑文を中心に― 道坂昭廣
[記念講演]
・ 六朝道教と仏教 東洋大学教授 山田 利明
○刊行物
『六朝学術学会報』第16集(3月)
2016(平成28)年
3月14日 第32回研究例会 於二松學舍大学
・ 南朝詩歌作品における「隴」―現実と想像のあいだ 西川ゆみ
・『 世説新語』の編纂意図 渡邉義浩
・ 魏晋時代の社の歴史的特質―当利里社残碑の検討を中心に― 福原啓郎
12月18日 第33回研究例会 於二松學舍大学
・ 許懋の学術とその時代 洲脇武志
・ 謝靈運「撰征賦」をめぐる若干の考察 原田直枝
・ 顔之推における仏教と儒教 渡邉義浩
6月18日 第20回大会 於二松學舍大学
・ 南朝斉梁艶詩に見える「内人」「中人」について 大村和人
・ 北朝における非漢語をめぐる雑考 池田恭哉
・「 文」概念の成立における班固の位置―六朝文論の原点として― 牧角悦子
・ 唐詩に見る六朝詩の受容
―王昌齢の「芙蓉楼送辛漸」詩の旅立つ人に伝言を託す構想と伝言内容を中心に 矢嶋美都子
[記念講演]
・ 六朝時代の都督府とその属僚たち 石井仁
刊行物
『六朝学術学会報』第17集(3月)
2017(平成29)年
◎例会
○3月17日(金)第34回研究例会 於 京都外国語大学
[報告]
・郊廟歌辞について 鄭月超
・宮廷場域與漢魏六朝才媛的文學活動 沈凡玉
・北魏における射の諸相 藤井律之
○12月2日(土)第35回研究例会 於 二松學舍大学
[報告]
・王延寿「魯霊光殿賦」における彫刻描写 木村真理子
・南朝斉梁「率爾」詩考 大村和人
・「史」の文学性―范曄の『後漢書』 渡邉義浩
◎大会
○6月17日(土) 第21回大会 於 二松學舍大学
[報告]
・徐幹の賢人論―「名実論」を媒介として― 長谷川隆一
・湯僧済「詠渫井得金釵」の問題点 山崎藍
・「幽通賦」諸注釈より見る後漢初期の賦創作について
栗山 雅央
・体系への憧れ―沈約が希求したもの 稀代麻也子
・六朝期の詩歌認識について―「詩」と「歌」の間― 佐藤 大志
・達意の為の仮構―『文選』巻四十五に載せる設論三篇をめぐって― 牧角 悦子
・杜甫における陶淵明 下定 雅弘
・謝霊運と廬陵王劉義真 大上 正美
◎刊行物
『六朝学術学会報』第18集(3月)
2018(平成30)年
6月16日 第22回大会・総会・評議員会(於 二松学舎大学 )
①初海 正明(栄光学園中学校・高等学校 国語科常勤講師)
「『老子』における「言」と「道」の関係性」
②三津間 弘彦
「前四史に見る夷狄列伝の展開」
③洲脇 武志(大東文化大学 非常勤講師)
「許懋の「封禅停止に関する建議」について」
④遠藤 星希(法政大学)
「李賀の詩にあらわれる?肩吾――「皇子」に唱和する詩人としての自己意識――」
⑤小池 直子(東洋大学 客員研究員)
「東晋中期の政局における皇太后の役割」
⑥狩野 雄(相模女子大学)
「芳る祖国――陸機「悲哉行」の芳香表現をめぐって」
⑦加固 理一郎(文教大学)
「晩唐の駢文の六朝文化との関わりについて」
⑧榎本 あゆち
「劉孝標と劉勰との関係について」
12月2日 第37回例会・評議員会(於 青山学院大学)
①青木竜一(東北大学大学院)
「後漢の相見儀制――「敬」の方式を中心に」
②山下紀伊子(早稲田大学大学院)
「郭象の「自然」―行為という視点から―」
③董子華(お茶の水女子大学大学院)
「沈約の「郊」――「遊」と「居」をめぐって」
④牧角悦子(二松學舍大学)
「かなしいうた――「歌以詠之」「歌以言志」の意味するもの」
2019(平成31・令和1)年
3月10日 第38回例会・評議員会(於 青山学院大学)
①池田恭哉(京都大学)
「辛彦之の没年をめぐる一考察」
②中澤仁(二松學舍大学大学院)
「庾信と宋玉 典故・用語による賦の分析」
③安藤信廣(東京女子大学名誉教授)
「徐陵の文学について」
6月15日 第23回大会・総会・理事評議員会(於 二松学舎大学)
①木村真理子(東北大学大学院)
「「魯霊光殿賦」における「猨」「狖」「熊」「胡人」「神仙」「玉女」等―先行する辞賦作品との違い―」
②武茜(東京大学大学院)
「『幽明録』の世界――劉義慶の天命・因果観について」
③李曌宇(東京大学大学院)
「韻字の消長から見る南朝文学」
④洲脇武志(愛知県立大学)
「王倹の礼学―穆妃の葬喪儀礼への対応を中心に」
⑤福原啓郎(京都外国語大学)
「六朝貴族制に関する一試論―『世説新語』を素材として―」
⑥矢嶋美都子(亜細亜大学)
「唐詩に見る六朝詩の受容―張九齢の「照鏡見白髪」詩を中心に」
⑦戸倉英美(公益財団法人東洋文庫研究員)
「「拒まれた女」中国古代篇―杜伯の故事をめぐって」
12月21日 第39回例会(於 亜細亜大学)
①柴棟(東北大学大学院)
「六朝隋唐における禅譲中の即位儀礼について――即位場所・告代祭天を手がかりに――」
②大立智砂子(明治薬科大学)
「陶淵明の詩文における、自詠の姿について」
③安藤信廣(東京女子大学名誉教授)
「『文選』以後の詩文と『万葉集』」
2020(令和2)年
3月19日 第40回例会 中止 2020年度 第24回大会・第41回・第42回 例会中止
2021(令和3)年
9月25日 第25回大会(Zoomによるオンライン)
○開会 13:00~
会長挨拶 安藤 信廣(東京女子大学名誉教授)
○研究発表 13:10~(各発表20分、質疑10分) ※途中休憩含む
①青木 竜一(東北大学大学院)(13:10~13:40)
曹操政権における軍師と軍師祭酒――魏科との関わりから――
司会 柳川順子(県立広島大学)
②陳 錦清(京都大学大学院)(13:45~14:15)
庾信の碑文と『弘仁本文館詞林』所収「郢州都督蕭子昭碑銘」について
司会 樋口泰裕(文教大学)
③伊藤 涼(早稲田大学大学院)(14:30~15:00)
郭象の思想における王弼の位置
司会 池田恭哉(京都大学)
④小野 響(日本学術振興会特別研究員PD(京都大学大学院))(15:05~15:35)
「黄龍国」小考
司会 洲脇武志(愛知県立大学)
⑤福田 素子(聖学院大学非常勤講師)(15:50~16:20)
『捜神後記』「武昌山毛人」の毛人とその後裔たち
司会 大村和人(徳島大学)
⑥佐藤 正光(東京学芸大学)(16:25~16:55)
六朝の詩風と詩語の継承―陶淵明、謝霊運から鮑照、謝朓へ―
司会 佐竹保子(大東文化大学)
○閉会の辞 渡邉義浩(早稲田大学)
2022(令和4)年 第43回例会・理事評議員会 (於 早稲田大学・ハイブリッド)
○会長挨拶 東京女子大学名誉教授 安藤信廣
○研究発表
①早稲田大学大学院 袴田郁一(13:10~14:10)
「裴松之『三国志注』に見られる史料批判の検討」
司会 福原啓郎(京都外国語大学名誉教授)
②文教大学 樋口泰裕(14:20~15:20)
「庾信「哀江南賦」における<わたし>について」
司会 鈴木崇義(國學院大學)
③大東文化大学 佐竹保子(15:30~16:30)
「五世紀における詩歌観の変質――その淵源とその波及――」
司会 坂口三樹(文教大学)
○閉会の辞 早稲田大学 渡邉義浩
9月10日 第26回大会 (於 早稲田大学・ハイブリッド)
○各種委員会 10:00~※詳細は各委員長にお問い合わせください。
○開会 13:00~
会長挨拶 安藤 信廣(東京女子大学名誉教授)
○研究発表 13:10~(各発表20分、質疑10分) ※途中休憩含む
①京都大学大学院 田尻 健太(13:10~13:40)
劉炫の生涯とその学問
司会 坂口三樹(文教大学)
②関西大学大学院 呉 雨清(13:50~14:20)
呉均の詩と『玉臺新詠』
司会 大村和人(徳島大学)
③愛知県立大学 洲脇 武志(14:30~15:00)
南朝における蔡氏
司会 渡邉義浩(早稲田大学)
④フェリス女学院大学 宋 晗(15:10~15:40)
鮑照詩の自然描写に関する考察
司会 鈴木敏雄(兵庫教育大学名誉教授)
○講演
青山学院大学名誉教授 大上 正美(15:50~16:50)
表現する阮籍――六篇の「賦」の基点から考える
司会 戸倉英美(東京大学名誉教授)
○閉会の辞 副会長 渡邉義浩(早稲田大学)
2023(令和4)年
3月4日 第44回例会(於 國學院大學・ハイブリッド)
○会長挨拶 東京女子大学名誉教授 安藤信廣
○研究発表
①徳島大学 大村和人(14:10~15:10)
「語りの表現から見た梁簡文帝蕭綱の詩風―「新成安樂宮」を中心に」
司会 池田恭哉(京都大学)
②東北大学大学院 潘宗悟(15:30~16:30)
「孫呉の対魏晋前線における都督区について――軍事戦略との関係を中心に――」
司会 洲脇武志(愛知県立大学)
○閉会の辞 亜細亜大学名誉教授 矢嶋美都子
9月9日 第27回大会(創立25周年記念大会) ・総会・理事評議員会(於東京大学・ハイブリッド)
○開会 9:45~
会長挨拶 安藤 信廣(東京女子大学名誉教授)
○研究発表 9:50~(各発表20分、質疑10分) ※途中休憩含む
①國學院大學大學院 名越 健人(9:50~10:20)
劉知幾の駢儷文批判について
司会 奈良女子大学 大平 幸代
②名古屋大学大学院 郭 $59E3(10:25~10:55)
任昉の詩文と『述異記』―「事」の観点からの一考察
司会 文教大学 坂口 三樹
③つくば国際大学 東風高等学校 宇賀神 秀一(11:05~11:35)
陶淵明「擬古」詩其一を巡って
司会 武庫川女子大学 狩野 雄
④志學館大学 西川 ゆみ(11:40~12:10)
江淹詩賦における悼亡と神女との関わりについて
司会 県立広島大学 柳川 順子
⑤愛知大学・愛知淑徳大学(非常勤講師)住谷 孝之(12:20~12:50)
六朝期の詩題における「寄」字の用法の成立について
司会 岡山大学 土屋 聡
○〇創立25周年記念企画
I 興膳先生の略歴ご紹介 東京女子大学名誉教授 安藤 信廣(13:50~14:00)
※記念講演「詩人と月――六朝から唐へ――」は中止となりました。
Ⅱ[記念企画――興膳宏先生の世界をふりかえる]
本学会第2代会長、興膳宏先生の研究世界を、その著書・論文によってふりかえり、本学会創立前後から今日に至るまでの六朝学術研究の流れ・問題意識の推移等をとらえなおし、今後の展望について考える機会とする。そのため、3名の会員より、興膳先生の著書・論文につき紹介のうえ、刊行当時の意義・現在的意義等を発表していただき、参加者も交えて意見交換を行う。
①広島大学 佐藤 大志(14:00~14:30)
『亂世を生きる詩人たち 六朝詩人論』に学ぶ六朝文学研究の可能性と課題
司会 國學院大學 鈴木 崇義
②早稲田大学 渡邉 義浩(14:30~15:00)
文学と儒教-『中国の文学理論』『中国文学理論の展開』を読み直す
司会 東京大学 谷口 洋
③京都大学 道坂昭廣(15:00~15:30)
「創作技法論の展開―『文心雕龍』から『文鏡秘府論』へ」から二つの<流れ>を見る
司会 大東文化大学 佐竹 保子
○総会(15:40~16:00)
○閉会の辞(16:00) 副会長 渡邉義浩(早稲田大学)
2024(令和5)年 (於 國學院大學・ハイブリッド)
3月16日 第45回例会
○開会(13:30~)
会長挨拶 東京女子大学名誉教授 安藤信廣
○研究発表
①早稲田大学大学院 佐藤大朗(13:35~14:20)
「裴松之『三国志注』受容――清代前期の李光地を題材に――」
司会 田中靖彦(実践女子大学)
②早稲田大学非常勤講師 伊藤涼(14:25~15:10)
「王弼の政治思想と郭象の政治思想」
司会 鈴木崇義(國學院大學)
③拓殖大学非常勤講師 王旭東(15:20~16:05)
「鬼怪を食べる話」
司会 戸倉英美(東京大学名誉教授)
④京都外国語大学名誉教授 福原啓郎(16:10~16:55)
「六朝時代の死生観に関する一考察―鎮墓文と墓誌の比較を中心に―」
司会 谷口洋(東京大学)
9月7日 第28回大会 ・総会・理事評議員会(於 早稲田大学・ハイブリッド)
○各種委員会 10:00~※詳細は各委員長にお問い合わせください。
○開会 13:00~
会長挨拶 安藤 信廣(東京女子大学名誉教授)
○研究発表 13:10~(各発表20分、質疑10分) ※途中休憩含む
①大阪大学人文学研究科研究生 鮑功瀚(13:10~13:40)
黄省曽本『謝康楽詩集』とその「古本」について$2014$2014温州における謝霊運の伝承を手がかりに
司会 坂口三樹(文教大学)
②東京大学特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD) 青木竜一(13:50~14:20)
後漢における天下観と交阯刺史部
司会 洲脇武志(愛知県立大学)
③徳島大学 大村和人(14:30~15:00)
斉梁艶詩と仏教
司会 佐竹保子(大東文化大学)
④東京大学 谷口洋(15:10~15:40)
漢魏における楚歌体について
司会 鈴木崇義(國學院大學)
⑤県立広島大学 柳川順子(15:50~16:20)
曹植の文学と西晋時代の人々
司会 戸倉英美(東京大学名誉教授)
○総会(16:30~16:50)
○閉会の辞 副会長 渡邉義浩(早稲田大学)
2025(令和6)年(於 國學院大學・ハイブリッド)
3月15日 第46回例会
会長挨拶 東京女子大学名誉教授 安藤信廣
趣旨説明 総合司会:東京大学教授 齋藤希史
國學院大學教授 上野誠
「万葉集を注釈してわかったこと―皆さんにお知恵借りたいです―」
明治大学等非常勤講師 会田大輔
「石に刻まれた思い―六朝文学の境をめぐって―」
京都大学人文科学研究所准教授 倉本尚徳
「六朝隋唐仏教史に関する近年の研究動向」
東京女子大学名誉教授・六朝学術学会会長 安藤信廣
「『万葉集』と六朝文学――大伴旅人と「竹林七賢」のことなど」
全体ディスカッション ディスカッサント:東京大学教授 谷口洋
閉会の辞 文教大学教授 坂口三樹
刊行物 『六朝学術学会報』第25集(3月)
9月6日 第29回大会 ・総会・理事会・評議員会(於 東京大学・ハイブリッド)
○各種委員会 10:00~
○総会(13:00~13:30)
○開 会 13:30~
会長挨拶 齋藤希史(東京大学)
○研究発表 13:40~(各発表20分、質疑10分)
※途中休憩含む
①フェリス女学院大学 宋晗(13:40~14:10)
「詩語としての煙の確立——劉宋文学の新動向——」
司会 堂薗淑子(愛知教育大学)
<休憩(10分)>
②青山学院大学 山崎藍(14:20~14:50)
「元稹「有鳥二十章」第十八首攷――鸚鵡譚の詩的転用」
司会 佐野誠子(名古屋大学)
<休憩(10分)>
③明治大学大学院 蔡忠義(15:30~16:00)
「魏晋六朝初唐の並称と古代日本におけるその受容について」
司会 道坂昭廣(京都大学名誉教授)
<休憩(10分)>
④長岡技術科学大学 長谷川隆一(15:40~16:10)
「君子は聖人になれるのか? ——性三品説の展開における顔回の位置づけを立脚点として―」
司会 和久希(二松学舎大学)
<休憩(10分)>
⑤早稲田大学 渡邉義浩「天監の改革と梁の貴族制」(16:20~16:50)
司会 川合安(東北大学)
○ 閉会の辞 渡邉 義浩(早稲田大学)
12月20日 第47回例会(オンライン開催)
ブックトーク 著者と読む―大村和人『六朝艶詩研究』―
六朝学術学会の今回の例会は、大村和人著『六朝艶詩研究』についてブックトーク的に実施します。著者自身が著書を語り、また、専門を同じくする読者、異にする読者がそれぞれどう読んだかを語ります。一冊の本に研究者がどのような思いを込め、出版に至ったのか、公刊された研究書がどのように読まれるのかについて、自由に語り合う機会とします。今回はオンライン形式の開催としましたので、お気軽にお聴きください。
司会:大平幸代
コメンテーター:住谷孝之・洲脇武志